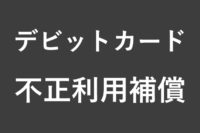ゆうちょPayは現金派にメリットあり ほかのスマホ決済との違いとは
※記事内に広告を含む場合があります
当サイトは更新を終了しました。
長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。
※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

ゆうちょ銀行が、スマホ決済アプリ「ゆうちょPay」をリリースしました。LINE PayやPayPayなどから、やや遅れての登場です。
ゆうちょPayとは、専用スマホアプリを使ってゆうちょ銀行の口座から直接支払いができるサービスです。
ゆうちょ銀行の口座とスマホがあれば誰でも利用でき、利用者は手数料が一切かかりません。
クレジットカードのような審査や年齢制限もないので、未成年の子供も使えます。
加盟店はまだ少ないですが、今後ゆうちょペイが使えるお店が増えると普及するかもしれません。
目次
ゆうちょPayの仕組み

ゆうちょPayを利用するためには、スマホ以外にゆうちょ銀行の口座が必要です。
ゆうちょダイレクト(ゆうちょ銀行のネットバンキングサービス)に登録していなくてもOKです。入会費や手数料も一切かかりません。
下記の3ステップだけで、ゆうちょペイ支払いができるようになります。
■ゆうちょPay 登録の流れ
- ゆうちょPayアプリをインストール(無料)
- アプリにゆうちょ口座を登録(記号・番号などを入力)
- 登録完了
ゆうちょ銀行のキャッシュカードが手元にあれば、1~3分程度で登録が完了します。
ゆうちょペイのID・パスワードを設定したあとは、iPhoneなら顔認証(Face ID)などでかんたんにログインできるようになります。
支払い方法は2種類

ゆうちょPayの使い方は、すでにリリースされているLINE PayやPayPayと同じです。
お店で会計をするときに「ゆうちょペイで」と言えば、下記いずれかの方法で支払いができます。
- バーコード決済
- ゆうちょPayアプリから支払い用バーコードを提示し、お店の読み取り機器でスキャンしてもらう。
- QRコード決済
- 会計時に、お店用のQRコードをゆうちょPayアプリで読み取る。
どちらの支払い方法になるかは、店舗によって異なります。
たとえばコンビニでは、こちらがバーコードを提示して読み取ってもらう「バーコード決済」が多いです。
普段の会計で使うバーコードリーダー(商品バーコードをピッと読み取る機器)を、バーコード決済でもそのまま利用できるからです。
他社のスマホ決済でも、コンビニではバーコードを読み取ってもらうケースがほとんどです。
一方、バーコード読み取り機器がないお店では、こちらが店舗のQRコードを読み取る「QRコード決済」が中心です。レストランなどの飲食店に多いです。
会計時に「ゆうちょペイで」と言い、タブレットなどで「読み取りお願いします」とQRコードを見せられたら、ゆうちょPayアプリでスキャンします。
「銀行Pay」全加盟店で利用できる
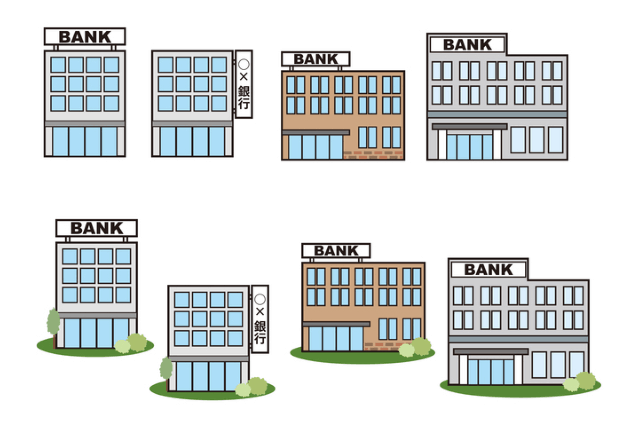
ゆうちょPayは、銀行Payというシステムをもとに作られたスマホ決済です。
銀行Payとは、銀行専用のスマホ決済サービスです。GMOペイメントゲートウェイという企業が、複数の銀行に提供しています。
銀行ペイの最大のメリットは、提携している銀行間で連携ができることです。
ゆうちょペイの加盟店ではないお店でも、銀行Payを利用している他行の加盟店ならゆうちょペイで支払えます。
たとえば、横浜銀行の「はまペイ」導入店舗でも、ゆうちょPayアプリで支払いが可能です。
■銀行Pay 参加金融機関(参加予定含む)
- ゆうちょ銀行
- 三井住友銀行
- 北陸銀行
- 北海道銀行
- 横浜銀行
- 十八親和銀行
- 福岡銀行
- 広島銀行
- 熊本銀行
- 沖縄銀行
今までの銀行Payは、地方銀行が中心でした。しかし、ゆうちょPayが参入することで加盟店が全国規模になる可能性もあります。
ゆうちょ口座を持っている人は、いつでも使えるようにしておいて損はないと思います。
手持ちの現金が少なかったり、ATMが近くになくてお金が下ろせなかったりしたときに役立ちます。
ゆうちょPayのメリット
ゆうちょPayのメリットは、「口座とスマホがあれば誰でも使える」というハードルの低さです。
さらに、ゆうちょ銀行の残高を確認できる、現金が引き出しやすくなるなどの利点もあります。
ゆうちょPayは、スマホ決済アプリでありながら、現金派の人にとっても便利なサービスといえます。
未成年も利用可、審査なし

ゆうちょ銀行の個人口座とスマホを持っていれば、誰でもゆうちょペイを利用できます。
クレジットカードのように審査がないので、年齢や収入の条件もありません。
未成年の子供や、クレジットカードを持てない人も手軽にキャッシュレス決済を始められます。
■クレジットカードを持てない人、審査に通りづらい人(一例)
- 未成年
- 高齢者
- 自己破産などをしてブラックリストに載っている人
- 生活保護受給者
- 非正規雇用
政府が発表している、2020年からのキャッシュレス決済のポイント還元措置にも活用できました。
ゆうちょ銀行の残高を確認できる

ゆうちょPayアプリでは、ゆうちょ銀行の口座残高をリアルタイムで表示できます。
アプリのインストール後、かんたんな口座認証手続きをすれば、いつでも残高照会できるようになります。ゆうちょPayを使う前に、残高をすぐにチェックできて便利です。
外出先でお金をおろしたいときも、わざわざATMに寄ったりネットバンキングにログインしたりする必要がなくなりす。
ゆうちょ銀行の「ゆうちょダイレクト残高照会アプリ」は、2020年4月末にサービスを終了しました。
銀行機能も、ゆうちょPayに集約していく方針なのかもしれません。
記事執筆時点では、ゆうちょPayでゆうちょ銀行口座の残高はチェックできますが、こまかい入出金履歴は確認できません。
将来的に、ゆうちょ銀行のネットバンキング機能がゆうちょPayに集約されれば、入出金履歴も見られるようになるかもしれません。
なお、利用履歴の確認はできます。
ポイント還元は0.25%
2022年2月1日からすべての店頭決済で、ゆうちょPayポイントが付与されることになりました。400円(税込)ごとに1ポイント、付与率は0.25%です。
ゆうちょPayポイントは、ゆうちょPayが利用できるお店で、1ポイント=1円として支払いに利用できます。
付与日はその都度でなく月2回、1日と16日に前月分が付与されます。ポイントの有効期限は1年間です。
ポイント還元率は高くないのであまり魅力的とはいえません。また有効期限も、2年とっているポイントサービスに比べると短いです。
とはいえ、ゆうちょPayが使えるお店が順次増えていることを考えると、あまり困らずに使い切れそうではあります。
病院でも使えるようになる可能性

銀行Payを開発しているGMOペイメントゲートウェイは、銀行ペイを病院の会計にも使えるようにしたいと発表しています。
ゆうちょPayも、いずれは病院の支払いに使えるようになる可能性が高いです。
日本は、現金払いしかできない病院がまだまだ多いです。大きな総合病院ではクレジットカード決済ができるようになってきていますが、スマホ決済の導入までは進んでいない状況です。
ゆうちょペイが多くの病院で使えるようになると、現金を引き出す手間なく治療費が払えるようになるかもしれません。
治療費が思ったより高く「手持ちの現金が足りない」と思ったときも、あわてずにゆうちょPayで支払えます。
ゆうちょPayのデメリット
一方、ゆうちょPayにはデメリットもあります。
記事執筆時点でわかっているデメリットは2点あります。
加盟店が少なく、調べづらい

ゆうちょPayが使えるお店は、ほかのスマホ決済アプリに比べるとまだまだ少数です。
リリース後しばらくして、近くの利用可能店舗を検索する機能はつきました。しかし、LINE PayやPayPayに比べると、まだまだ普及していない印象です。
ゆうちょペイが使えるお店の一例は以下の通りです。当初はドラッグストアや家電量販店がメインでしたが、コンビニ、ファミリーレストラン、小売りと順次増えています。
■ゆうちょPayが使えるお店(一部)
- ミニストップ
- セブンイレブン
- ウエルシア薬局グループ
- エディオン
- ヤマダ電機
- ケーズデンキ
- 松屋
- 東急ハンズ
店舗がキャッシュレス決済を導入する際は、加盟店手数料がかかります。ゆうちょPayの加盟店手数料は非公開ですが、スマホ決済の加盟店手数料の相場は売上の3%前後です。
クレジットカードの加盟店手数料に比べると安いものの、この手数料がネックになってキャッシュレス決済を導入できない中小店舗も多いです。
スマホ決済大手のPayPayは、加盟店手数料が無料になるキャンペーンで積極的に店舗網を拡大しています。
クレジットカードは登録できない
ゆうちょPayは原則、ゆうちょ銀行口座と連携して使います。クレジットカードやデビットカードからの支払いはできません。
ゆうちょPayは、支払うと銀行口座から即時引き落としとなります。そのため、口座残高が足りないと支払いができません。
クレジットカード決済できるスマホ決済アプリは、支払い時点で口座残高がなくても支払いができます。スマホ決済の利用額は、クレジットカードの利用代金と一緒に翌月請求となる仕組みです。
ゆうちょPayは現金派の人向け

ゆうちょPayのメリット・デメリットを見ると、どちらかというと現金派の人向けのアプリだという印象でした。
キャッシュレス決済ならではの、ポイント還元やクレジットカード連携といったメリットはないからです。
逆に、スマホ決済のこまかい仕組みが理解しづらい人にとっては、シンプルで使いやすいスマホ決済と言えます。
クレジットカードはお金を使いすぎそうで怖い、ゆうちょ銀行のメイン口座をそのまま使いたいという人にも向いています。
何より、「ゆうちょ銀行のスマホ決済」という安心感も大きいです。
現金を引き出す機会が多い人にとって便利という点でも、ゆうちょPayは現金派の方向けです。
デビットカードも持っておいた方が安心かも

とはいえ、ゆうちょPayはまだまだ使えるお店が少ないのが現状です。現金派の人はゆうちょPayだけでなく、デビットカードも持っておくと安心です。
デビットカードとは、支払いをすると銀行口座から即時引落としになるカードです。
後払いのクレジットカードと違い、口座残高以上の支払いができないのが特徴です。ゆうちょPayに近い使い方ができます。
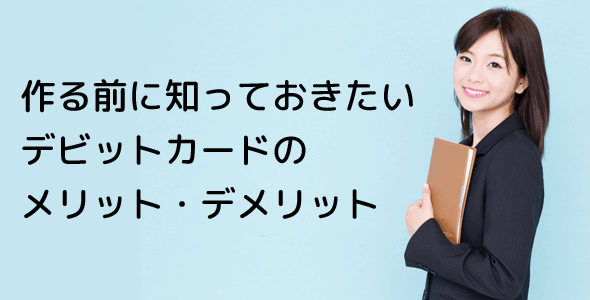
あわせて読みたい:
デビットカードとは?知っておきたい3つのメリット・デメリット